津波シェルターとは?メリット・デメリットやおすすめの家庭用シェルターを紹介

近年、東日本大震災や能登半島地震をはじめ、大規模な地震や津波被害が相次いでいます。
さらに、今後30年以内に高い確率で発生するとされる南海トラフ巨大地震では、最大で20メートルを超える津波が想定されており、「自宅でどう身を守るか」は誰にとっても現実的な課題となっています。
このような背景から注目を集めているのが「津波シェルター」です。
とはいえ、「そもそも津波シェルターとはどんなものなのか」「どんな種類があるのか」「価格はどれくらいするのか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、津波シェルターの基本知識から種類・メリットデメリット・価格相場・おすすめ製品までわかりやすく解説します。
大切な家族や自分の命を守るための備えとして、ぜひ参考にしてください。
■ 目次
津波シェルターとは?

津波シェルターとは、津波による浸水や瓦礫の衝突から人命を守るために設計された避難用設備のことです。
従来は自治体や企業が防災インフラとして整備するイメージが強かったものの、近年では個人や家庭向けの小型モデルも普及し始めています。
形状や仕組みはさまざまで、大きくは「水に浮かんで流されないように設計された浮体式タイプ」と「地下や屋外に設置する固定型タイプ」の2種類があります
また最近では、防水性・気密性を備えたカプセル型や、屋内に設置できるタイプなどさまざまな商品が登場し、都市部や高齢者世帯からも関心を集めています。
家庭用の津波シェルターが注目されている理由
家庭用の津波シェルターが注目を集めている背景には、南海トラフ巨大地震のリスクが高まっていることが挙げられます。
政府の想定によると、南海トラフ巨大地震の発生確率は今後30年以内で70〜80%とされ、沿岸地域では最大20メートル級の津波が到達する可能性があるとも言われています。
さらに、津波は発生からわずか数分で押し寄せることも多く、高齢者や子どもがいる家庭の「逃げ遅れ」が懸念されています。
その点、津波シェルターを家の敷地内や屋内に設置すれば、スムーズな避難が可能となり、救助が到着するまでの安全空間を確保可能です。
また、近年は家庭向けに導入しやすいモデルも増えていることから、従来は企業や公共施設向けと考えられていた津波シェルターが、一般家庭でも導入できる「現実的な選択肢」として注目されているのです。
家庭用津波シェルターの種類
家庭用の津波シェルターといっても、形状や設置方法はさまざまで、それぞれ特徴や強みが異なります。
代表的なのは「水に浮いて避難できるタイプ」と「地下や屋外に設置するタイプ」です。どのタイプを選ぶかは、住んでいる地域や設置スペース、予算によって大きく変わってきます。
ここでは、それぞれのタイプの特徴やメリット・デメリットについて、詳しく見ていきましょう。
浮かぶタイプ

浮かぶタイプは、津波による浸水時に水面に浮上して安全を確保できるシェルターです。大きく分けて「カプセル型」と「ボート型」があります。
| タイプ | 特徴 |
| カプセル型 | 強化樹脂やスチールで作られた密閉構造を持ち、外部からの衝撃や瓦礫の衝突に耐えられる設計が特徴です。内部は気密性が高く、酸素ボンベや換気装置を備える製品もあり、数時間〜半日程度の滞在が可能とされています。 |
| ボート型 | 屋根がなく、見た目は救命ボートに近いタイプです。完全な密閉はできませんが、その分軽量で扱いやすく、価格も比較的抑えられるのが特徴です。 |
いずれのタイプも、津波到達までの短時間で迅速に避難できることが最大の強みです。
特に沿岸部や川沿いに住んでいる世帯にとっては、「逃げ遅れ防止」の有力な選択肢といえるでしょう。
ただし、浮かぶタイプはあくまでも水没を防ぐ目的で設置される点に注意が必要です。地下型と比べると耐久力は劣ることを覚えておきましょう。
津波シェルター内の酸素はどうやって供給されるの?
津波シェルターに避難した際に気になるのが「中で呼吸はできるのか」という点です。
特にカプセル型のように密閉度が高いタイプでは、酸素をどのように確保するかが重要になります。
一般的な家庭用シェルターでは、以下のような方法で酸素を供給する仕組みが採用されています。
- 酸素ボンベの搭載
シェルター内に酸素ボンベを設置し、必要に応じて内部に酸素を送り込む方式です。短時間の滞在であれば十分対応可能で、比較的シンプルな仕組みといえます。
- 換気システム装置の搭載
外部から空気を取り込み、フィルターを通して内部に送るシステムです。粉じんや有害物質を除去できるモデルもあり、より長時間の滞在に適しています。
さらに、高性能モデルでは二酸化炭素(CO₂)除去装置を備えたものもあり、内部の空気環境を安定させることが可能です。こうした設備を備えることで、救助が到着するまでの数時間〜半日程度を安全に過ごせるよう設計されています。
地下に設置するタイプ

地下に設置するタイプの津波シェルターは、地中に設置することで津波の直接的な衝撃から身を守るタイプです。地下にあるため、津波の水圧や瓦礫の直撃を受けにくく、耐久性に優れている点がメリットといえるでしょう。
また、内部は気密性を高めた設計になっており、防水性能も◎。酸素ボンベや換気装置を備えることで、数時間〜半日の滞在も可能です。
ただし、地下型には課題もあります。まず、設置には庭や土地のスペースが必要で、都市部の住宅では導入が難しい場合があります。また、大規模な掘削工事が伴うため、費用や工期が浮体式より高くなる可能性が高いでしょう。
地下型は「高い耐久性」と「確実な防水性」を兼ね備える一方、コストや設置条件に制約があるため、導入には十分な検討が必要です。
家庭用津波シェルターのメリット
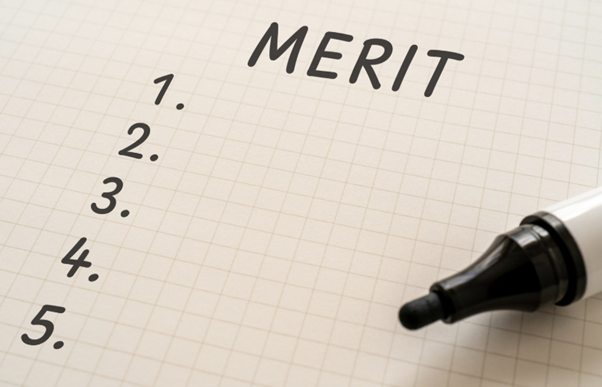
家庭用津波シェルターの最大のメリットは、津波が発生した際に自宅からすぐに避難できる 点です。
津波避難で最も大きな課題となるのは「逃げ遅れ」であり、特に高齢者や足の不自由な方、小さな子どもがいる家庭では高台や避難所まで移動するのが困難なケースも少なくありません。
その点、自宅にシェルターがあれば、移動距離はほとんどなく、数分で安全な空間に入ることができます。
さらに、シェルターは水圧や瓦礫の衝撃に耐えられる設計になっており、安全な空間で救助を待てるのも大きなメリットです。
このように、家庭用津波シェルターは逃げ遅れを防ぐだけでなく、命を守る最後の砦として、現実的かつ効果的な備えといえるでしょう。
家庭用津波シェルターのデメリット
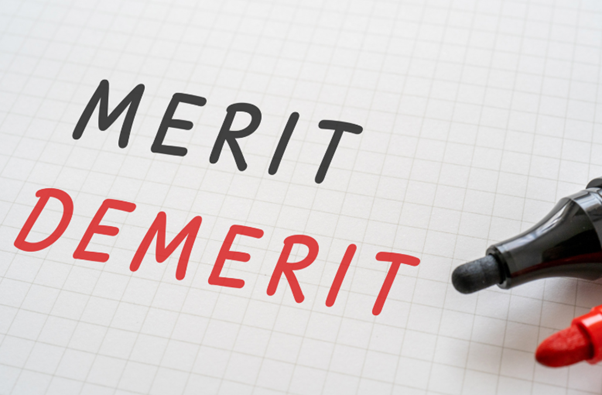
家庭用津波シェルターは有効な備えである一方で、導入にあたってはいくつかのデメリットも理解しておく必要があります。
まず挙げられるのが導入コストです。シェルター本体の価格は数十万円から数百万円と幅広く、さらに設置工事費用が加わると総額はさらに膨らみます。
特に地下型や大型タイプは、土地の掘削や基礎工事が必要なため、初期費用が高額になりがちです。
次に、設置場所の制約があります。設置には庭や駐車場などの広いスペースが必要な場合が多く、都市部の狭小住宅やマンションでは導入が難しいこともあります。
さらに、日常生活での扱いづらさも無視できません。サイズによっては生活動線を妨げたり、敷地利用の自由度を下げるケースもあるでしょう。
加えて、酸素ボンベや換気装置を搭載したモデルでは、定期的な点検や部品交換といった メンテナンスの手間も必要です。
このように、コスト・スペース・維持管理といった課題があるため、津波シェルターは「設置環境や予算に合うかどうか」を慎重に検討することが重要です。
家庭用の津波シェルターの値段
家庭用津波シェルターの価格は、タイプや仕様によって大きく異なります。
一般的な相場は数十万円〜数百万円とされ、簡易的なボート型から本格的なカプセル型まで幅広いラインナップがあります。
それぞれのタイプごとの費用目安は、以下のとおりです。
| タイプ | 特徴 | 価格帯の目安 |
| ボート型 | 軽量・簡易、屋根なし | 約30万円〜150万円 |
| カプセル型 | 密閉式・酸素設備搭載可 | 約80万円〜1,000万円 |
| 地下型 | 掘削工事が必要、高耐久 | 数百万円〜数千万円 |
また、費用は「本体価格+設置工事費」で考える必要があり、搬入や基礎工事の有無によって総額が大きく変動します。
そのため、導入を検討する際は必ず複数の業者に見積もりを依頼し、総額で比較することが大切です。
おすすめの家庭用津波シェルター4選
家庭用津波シェルターといっても、メーカーや製品によって構造や機能は大きく異なります。
そこでここでは実際に販売されている代表的な4製品を取り上げ、それぞれの特徴や価格帯を整理しました。
製品選びの参考として、用途や設置環境に合ったタイプを比較してみましょう。
タスカル|株式会社ミズノマリン
「タスカル」は株式会社ミズノマリンが開発したカプセル型の津波シェルターです。
高台や避難タワーまでの避難が難しい地域や、家族に高齢者・ペット・災害時要援護者がいる世帯に適した家庭用モデルとして注目されています。
設置は軽自動車1台分のスペースがあれば可能で、本体はセルフライディング(自動復帰)機能と不沈構造を備え、漂流中に横転しても自動的に復元することができます。さらに船体全周には大型フェンダーを装備しているため、瓦礫や船体との衝突によるダメージを軽減可能です。
また、標準でエントリードア2カ所、昇降ラダー、シートベルト、ビルジポンプなどが備わっており、防水ライトやアンカーといった付属品も充実。さらに、無線機や救難食料などを追加できるオプションも揃っており、実際の災害時に安心して利用できる仕様となっています。
| 製造会社 | 株式会社ミズノマリン |
| タイプ | カプセルタイプ |
| サイズ | 2.10m × 1.83m × 1.70m~ |
| 価格 | 要問合せ |
| 公式サイト | タスカル |
SAFE+|株式会社タジマモーターコーポレーション|
「SAFE+(セーフプラス)」は、レーシングドライバーとして知られる田嶋信博氏が培った安全技術を応用して開発された浮揚式津波・洪水対策用シェルターです。
最大の特徴は、強靭なFRP(繊維強化プラスチック)モノコック構造。レーシングカーにも使われる素材を採用しており、10m/sの衝撃試験や3mの落下試験、180度転覆からの復元試験をクリアしています。
内部には4点式シートベルトとヘッドレストを完備し、漂流中の衝撃や転覆時の安全を確保。床下には独立気泡の発泡プラスチック浮力体が組み込まれており、万一浸水しても沈まない不沈構造を実現しています。
また、箱型の形状は室内を広々と使えるだけでなく、ドア位置が低く設定されているため乗り降りも容易。平常時には休憩所・備蓄倉庫・勉強部屋・救護所などに活用できるのもメリットです。
| 製造会社 | 株式会社タジマモーターコーポレーション |
| タイプ | カプセルタイプ |
| サイズ | 3.90m × 2.15m × 2.15 m~ |
| 価格 | 5,940,000 円(税込)~ |
| 公式サイト | SAFE+ |
ソトチカ|株式会社大浜組
「ソトチカ(SOTOCHIKA)」は、株式会社大浜組が手がける地下型の津波シェルターです。
FRPと鋼板を組み合わせた二重殻構造を採用しており、円柱型構造によって外圧や地圧を均等に分散させることで、高い耐震性を実現しています。
また、入口の防水ハッチによって浸水や湿気をシャットアウトすることで経年劣化を防ぎ、長期間に渡って性能を維持することが可能です。
内部は全高約1.9m〜2.1mのゆとりある空間で、立ったままでも過ごせる設計なのも魅力。内壁には調湿塗料を用いており、結露防止・防カビ・消臭といった機能も兼ね備えています。
さらにオプションで酸素供給装置や二酸化炭素吸着剤を導入でき、最長15時間程度の滞在が可能。災害時の避難シェルターとしてはもちろん、備蓄庫や防災倉庫としても日常的に活用できます。
| 製造会社 | 株式会社大浜組 |
| タイプ | 地下型 |
| サイズ | 要問合せ |
| 価格 | 要問合せ |
| 公式サイト | ソトチカ |
津波シェルター CL-HIKARi(CLヒカリ)|株式会社光レジン工業
「CL-HIKARi(シーエル・ヒカリ)」は、国内自社工場で製造される純国産の津波シェルターです。
特筆すべきは、特許取得済みの自動スイング構造。水上でシェルターが浮遊した際、重心が自動的に傾き、ハッチが常に上部に位置する仕組みになっています。これにより、水上での救出・脱出が容易になり、閉塞感の軽減にもつながります。
また、32トン以上の耐荷重強度を備えているのも特徴です。これは、木造2階建て住宅3軒分の重量に相当し、上から強い圧力を受けても押し潰されない堅牢さを誇ります。
そのほか、安全性を高める工夫が随所に施されているのも魅力です。たとえば、扉には4つのロックハンドルを備え、外部からの衝撃で開く心配がありません。さらに、外部救助用の「明かり窓」を搭載しており、内部から開けられない状況でも外部から救助が可能です。
| 製造会社 | 株式会社光レジン工業 |
| タイプ | カプセルタイプ |
| サイズ | 1740mm × 900mm ×1000mm |
| 価格 | 880,000円(税別) |
| 公式サイト | CL-HIKARi(CLヒカリ) |
家庭用津波シェルターの選び方
津波シェルターは「万が一の命を守る設備」であるため、購入時には価格だけでなく、安全性や信頼性を重視して選ぶ必要があります。
特に家庭用モデルは製品によって耐久性や設置方法が大きく異なるため、事前にしっかりと比較検討しておくことが重要です。
そこでここでは、導入を検討する際に押さえておきたいポイントを順番に紹介します。
これまでの導入実績が豊富な企業を選ぶ

津波シェルターを選ぶ際に最初に確認したいのは、そのメーカーや施工会社がどれだけの導入実績を持っているかです。
津波シェルターはまだ広く普及しているわけではないので、実際の災害時の運用や設置事例が少ない場合もあります。
その中で、官公庁や自治体、企業などへの納入実績が豊富なメーカーであれば、設計や安全試験のノウハウが蓄積されており、安心感があるでしょう。
また、過去に大規模な地震・津波を想定した実証試験を行っているかも大切なチェックポイントです。
さらに、実績が多い企業はアフターサービスやメンテナンス体制もしっかりしているため、導入後の不安を軽減できます。価格だけで判断せず、これまでの信頼性・実績を重視することが「後悔しない選び方」につながるでしょう。
耐久性が十分か確認する

津波シェルターを選ぶ際には、必ず耐久性と安全性を確認しましょう。
シェルターは津波の強烈な水圧や漂流物の衝突に耐えられる設計でなければ、命を守る役割を果たせません。そのため、メーカーがどのような強度試験や安全性能テストを行っているかを事前に調べることが大切です。
たとえば、圧力試験で数十トンの荷重に耐えた実績や、水面落下試験、転覆からの復元試験をクリアしているかは重要な判断基準となります。
また、素材にFRP(繊維強化プラスチック)や鋼板を用いた二重構造など、耐久性を高める工夫がされているかも注目すべきポイントです。
さらに、気密性や防水性能もチェックしましょう。完全密閉状態でも内部環境を保てる設計であれば、浸水のリスクを大幅に減らせます。
長期間使い続ける設備だからこそ、単なるカタログスペックだけでなく、実証データや試験結果を公表しているメーカーを選ぶのが安心です。
設置・移動のしやすさを考慮する

家庭用津波シェルターを導入する際には、設置や移動のしやすさも考慮する必要があります。
津波シェルターは、種類によって重量やサイズが大きく異なり、設置工事の規模や搬入方法も変わってきます。
たとえば、地下型は耐久性に優れているものの、大規模な掘削工事や基礎工事が必要で、費用や工期がかかります。
一方、浮揚式やカプセル型は比較的コンパクトで、庭や駐車場など限られたスペースにも設置できるのが利点です。中には軽自動車1台分のスペースがあれば施工可能なモデルもあり、都市部の住宅にも導入しやすくなっています。
また、災害時の利用を考えると「どの場所に置けば最短で避難できるか」も重要です。自宅からすぐにアクセスできる場所に設置できれば、逃げ遅れを防ぐ確率は格段に上がります。
さらに、搬入や設置後に移動できるモデルであれば、引っ越しなどにも柔軟に対応できるでしょう。
まとめ
津波シェルターは、南海トラフ巨大地震などの切迫リスクが高まる昨今、「逃げ遅れ」のリスクを軽減し、自宅で命を守るための現実的な備えとして注目されています。
近年では、家庭に導入できるモデルも増えており、浮揚式カプセル型やボート型、地下設置型など、住環境や予算に応じた選択も可能です。
しかし、設置費用は数十万〜数百万円と高額になりやすく、設置スペースやメンテナンスの課題がある点には注意しなければなりません。そのため、導入を検討する際は「信頼できる実績のあるメーカーを選ぶ」「耐久性や安全試験の内容を確認する」「設置条件に合うかを見極める」など、選び方のポイントを抑えておくようにしましょう。
万が一のときに家族を守れるかどうかは、事前の備えがあるかにかかっています。「有事に備えてシェルターを購入しようか悩んでいる」という方は、ぜひこの記事をきっかけに津波シェルター導入を検討してみてはいかがでしょうか。
困ったことがあれば、ぜひHANAREにご相談ください。




