台湾有事による日本への影響をわかりやすく解説!起こる可能性や今からできる対策も

近年、国際情勢の変化から中国と台湾、さらにはアメリカの関与までが懸念される「台湾有事」。
もし台湾で中国との衝突が現実化し、アメリカが介入するとなれば、日本は地理的にも経済的にも無関係ではいられません。
しかし「実際のところどんな影響が出るの?」「台湾有事に向けて備えておくことはある?」といった疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
本記事では、台湾有事が日本に与える具体的な影響や発生の可能性を整理し、私たちが今からできる対策についてわかりやすく解説します。
将来の不安に備えるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
■ 目次
台湾有事による日本への影響
台湾有事が起きたとき、日本への影響として考えられるのは主に以下4つです。
- 海上輸送ルートへの影響
- 半導体産業への影響
- 台湾や中国に住む日本人への影響
- 台湾に近い地域への影響
ここからは、それぞれの影響について詳しく解説します。
海上輸送ルートへの影響
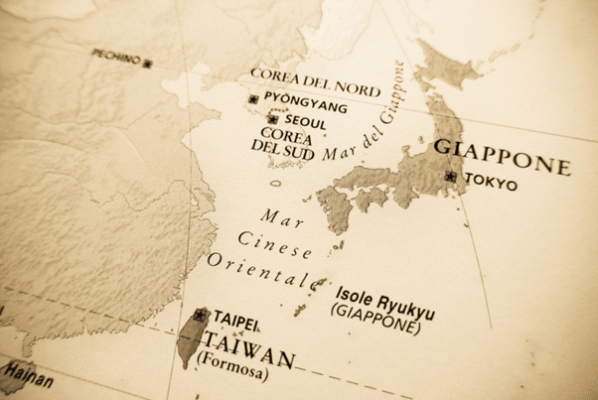
台湾有事による日本への影響として、最も大きいとされるのが海上輸送ルートへの影響です。
台湾周辺の海域は日本にとって「海の大動脈」ともいえる重要な輸送路であり、石油や天然ガス、食料品などの大半がこのルートを経由しています。
そのため、もし台湾有事によって台湾海峡や南シナ海が封鎖されれば、日本は輸入コストの上昇や供給不足に直面する可能性が高いのです。
特に原油や液化天然ガスの価格は国際市場で敏感に反応し、燃料費や電気料金の高騰につながるおそれがあります。
また、食料品や日用品の輸送コストも増大し、私たちの生活に直接影響を及ぼすことになるでしょう。
半導体産業への影響
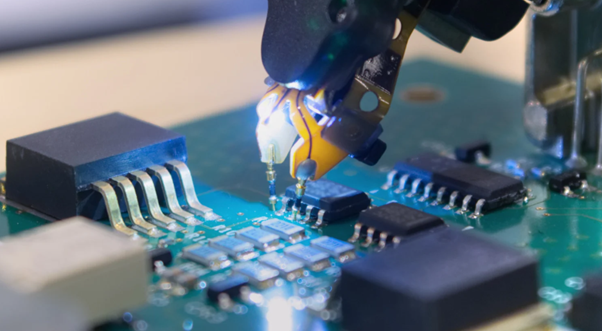
台湾有事が発生した場合、日本や世界経済に最も深刻な影響を与えるのが半導体の供給不足です。
台湾にはTSMCをはじめとする世界有数の半導体メーカーが集中しており、日本の自動車・スマートフォン・家電産業もその部品に大きく依存しています。
そのため、もし台湾有事によってこれらの生産や輸出が止まれば、部品供給が途絶え、日本の製造業全体に大規模な混乱が広がる可能性があります。
実際、過去には新型コロナによって一時的に半導体の供給が滞り、自動車の減産や電子機器の価格上昇が起きました。
これを踏まえると、有事となった際はその比ではない影響が予想されるでしょう。
また、半導体は単なる工業製品ではなく、防衛産業にも欠かせない基幹技術です。長期間供給がストップすれば、経済だけでなく安全保障上の大きなリスクにもなりかねません。
つまり台湾有事は、日本の産業競争力や日常生活の安定を揺るがす重大な脅威といえるのです。
台湾や中国に住む日本人への影響
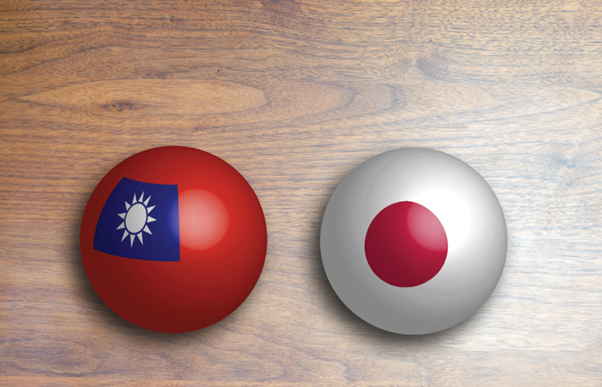
現在、台湾には約2万人、中国には約9万人以上の日本人が在留しており、有事の際には避難や帰国が必要になる可能性があります。
特に台湾は戦闘の舞台となるおそれがあるため、航空便や船舶による帰国ルートが遮断され、スムーズな退避が難しくなる可能性もあるでしょう。
また、中国に住む日本人に関しては、別のリスクも指摘されています。
中国では2023年に改正された「反スパイ法」が施行され、外国人ビジネスマンや研究者が拘束されるケースも報告されています。
そのため、有事の際には政治的緊張が高まり、日本人が不当に拘束されるリスクも否定できません。
台湾に近い地域への影響

台湾有事が発生した場合、地理的に近い沖縄や南西諸島の住民も直接的な影響を受けると考えられます。
特に沖縄は台湾からの距離が近く、在日米軍基地も集中しているため、有事の際には軍事拠点として重要視される可能性が高いです。
そのため、攻撃対象となるリスクもゼロではなく、住民の安全確保が大きな課題となります。
実際に沖縄県や周辺自治体では、台湾有事を想定した避難計画が策定されており、約12万人の島民が一時的に避難を余儀なくされるシナリオも検討されています。
| いわゆる「台湾有事」などを念頭に、政府は、沖縄の離島からの避難計画を初めてまとめ公表しました。住民らおよそ12万人を6日程度で避難させ、九州や山口県の合わせて32の市や町で受け入れるなどとしています。 |
さらに、観光業や物流といった地域経済への打撃も避けられません。
台湾との近接性が強みでもある沖縄にとって、有事はそのままリスクとして跳ね返ってくる可能性があるのです。
日本への影響を踏まえて、今から対策できること
台湾有事は国際情勢の問題ですが、その影響は日本で暮らす私たちの日常生活にも及びます。そのため、台湾有事が起きたときに混乱しないためにも、日ごろから備えておくことが大切です。
ここからは、日本への影響に備えてできることとして、以下4つを紹介します。
- 物流・流通の混乱に備える
- 避難場所や非常用持出袋の用意
- 家庭用シェルターの導入
- 経済・金融リスクに備える
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
物流・流通の混乱に備える

台湾有事への対策として最初に考えるべきは、物流や流通の混乱による物資不足への備えです。
台湾有事が起きれば海上輸送ルートが不安定になり、食料や燃料などの輸入品が不足する可能性があります。
特に日本は食料自給率が低いため、輸入が止まればすぐに生活への影響が出るでしょう。
そのため、各家庭では最低3日分、できれば1〜2週間分の食料と水を備蓄することが推奨されます。
飲料水は1人1日3リットルを目安に確保し、食料はレトルト食品や乾麺、缶詰など長期保存できるものを中心に揃えると安心です。
また「ローリングストック方式」で日常的に消費しながら備蓄を維持すれば、無駄なく継続的に備えを整えることができます。
有事に限らず自然災害への備えにも役立つため、生活防衛策として取り入れておくとよいでしょう。
避難場所や非常用持出袋の用意

台湾有事が発生した場合、状況によっては避難が必要となるケースも考えられます。
そのため、日頃から避難場所の確認と非常用持出袋の準備を整えておくことが大切です。
自治体が指定する避難所の場所や、家族で集合するポイントを事前に話し合い、避難ルートを共有しておきましょう。
また、非常用持出袋には飲料水や非常食、懐中電灯、モバイルバッテリー、常備薬、衛生用品、簡易トイレなど、最低限の生活を支える物資を入れておくと安心です。
加えて、貴重品や身分証のコピー、家族の連絡先リストも入れておくと、通信障害時に役立つでしょう。
さらに、家族間での連絡手段をあらかじめ決めておくことも欠かせません。災害用伝言ダイヤルやSNSを利用した安否確認方法を共有すれば、混乱の中でも冷静に行動できるはずです。
家庭用シェルターの導入

台湾有事のように、予測できない大規模な危機に備える方法のひとつが家庭用シェルターの導入です。
日本では公的な核シェルターや防空壕の整備がほとんど進んでいないため、最悪の事態に備えるには自宅に避難空間を確保することが現実的な選択肢となります。
家庭用シェルターには、地下に設置するタイプや、屋内に置ける小型タイプなどがあり、中には気密性・換気装置・フィルターを備え、放射性物質や有害ガスから身を守れるモデルも存在します。
また、耐震性に優れたシェルターも多いため、台湾有事はもちろん、近年高まっている大地震への備えとしても有効です。
なお、HANAREでは日本での導入実績No.1のWNIシェルターを取り扱っており、ご予算や希望に合わせた提案が可能です。「有事に備えて自宅に安心できる避難先を確保したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
経済・金融リスクに備える
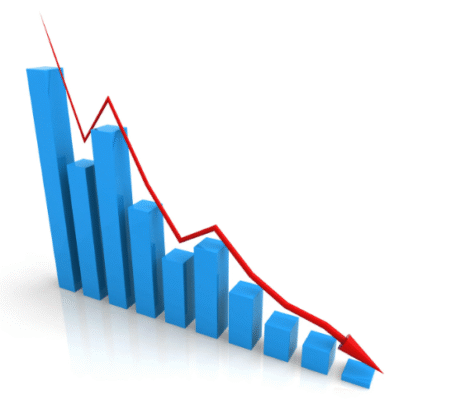
台湾有事が発生すれば、海上輸送や貿易が滞ることで物価が急激に上昇する可能性があります。
原油や天然ガスなどエネルギー価格の高騰は電気代やガソリン代にも直結し、さらに食料品や日用品の値段も上がるでしょう。
こうした生活コストの上昇に備えるためには、経済・金融面での対策も欠かせません。
まず重要なのは、生活防衛資金の確保です。収入が不安定になっても数ヵ月は生活を維持できるよう、生活費の3〜6ヵ月分を現金や流動性の高い預金として準備しておくと安心です。
加えて、日用品や保存の効く食料を「ストック買い」しておくことで、急な値上げ時にも慌てずに済みます。特にトイレットペーパーや乾麺、缶詰などは供給不足となる可能性が高いので、あらかじめ余裕をもって購入しておきましょう。
また、資産運用をしている場合は、有事のリスクに備えて分散投資を見直すことも大切です。安全資産への一部シフトを検討するなど、経済的な衝撃を緩和できる準備を整えておきましょう。
台湾有事が起こる可能性は?起こるとしたらいつ?
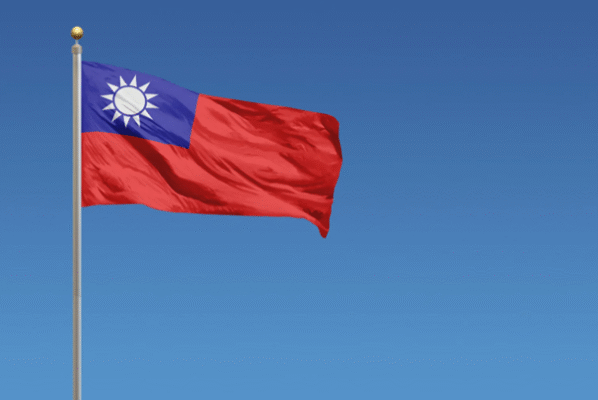
台湾有事が実際に起こるかどうかについては、専門家の間でも意見が分かれています。
しかし、現状では「すぐに起こる可能性は低い」との見解が多く、中国自身も経済的リスクや国際的な孤立を避けたい思惑があるといわれています。
一方で、中国は台湾統一を「国家の核心的利益」と位置づけており、軍事力の近代化を急速に進めているのも事実です。
そんな中で、台湾有事が起こる時期として言及されるのが「2027年説」です。
2027年は、中国人民解放軍が創設100周年を迎える年であり、習近平政権が軍の近代化をこの年までに達成する目標を掲げていることに由来します。
ただし、2027年に必ず有事が発生するという保証はありません。むしろ、国内外の情勢によって先延ばしされる可能性が高いともみられています。
結論としては、台湾有事が「いつ起こるか」を断定することはできません。
だからこそ、過度に不安を抱くのではなく、中長期的なリスクとして冷静に備える姿勢が大切だといえるでしょう。
台湾有事はいつ起こる?2025年・2027年説や個人ができる備えについて解説
台湾有事による日本への影響に関するFAQ
近年は台湾有事という言葉を耳にする機会が増えていますが、実際にどのような出来事を指すのか、そして日本がどんな立場にいるのかなどを具体的に理解できていない方も多いのではないでしょうか。
そこでここでは、台湾有事についてのよくある疑問をQ&A形式で整理し、わかりやすく解説します。似たような疑問をお持ちの方は、ぜひこの機会に疑問を解消してください。
そもそも台湾有事とは何ですか?
台湾有事とは、一般的に中国と台湾の間で軍事的な衝突が発生することを指します。
中国は台湾を「自国の一部」と位置づけており、将来的な統一を目指してきました。
一方、台湾は独自の民主的な政治体制を持ち、アメリカをはじめとする国際社会との関係を強めています。
このような立場・主張の違いから、両者の対立が続いており、軍事的な衝突が懸念されているのです。
台湾有事については、以下の記事でも詳しく解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
台湾有事とは?日本への影響や起こる可能性、個人でできる備えをわかりやすく解説
台湾有事に対して日本はどんな立場をとっていますか?
日本は「台湾有事」を自国の安全保障に直結する重大な問題として認識しています。
また、政府は一貫して「台湾問題は平和的に解決されるべき」という立場を示し、武力による現状変更にも反対してきました。日米同盟の枠組みの中でも、台湾海峡の平和と安定を維持することは日本の安全にも欠かせないと明言しています。
一方で、日本は台湾を国家として公式に承認しているわけではなく、あくまで「非政府間の実務関係」を維持する形をとっています。
| 問10.台湾に関する日本の立場はどのようなものですか。
台湾との関係に関する日本の基本的立場は、日中共同声明にあるとおりであり、台湾との関係について非政府間の実務関係として維持してきています。政府としては、台湾をめぐる問題が両岸の当事者間の直接の話し合いを通じて平和的に解決されることを希望しています。 引用元:よくある質問集|外務省 |
これは1972年の日中国交正常化以降の基本方針であり、中国との外交関係を重視しながらも、台湾との経済・文化交流を拡大してきました。
つまり日本の立場は、「台湾との友好・協力を重視しつつ、中国との関係も維持する」というバランス外交にあります。
ただし、中国が台湾に対して軍事的行動を起こした場合、米軍との連携や自衛隊の対応が求められる可能性が高く、日本が巻き込まれるリスクも否定できません。
直近では、トランプ政権が日本に対して台湾有事における役割の明確化を求めたとの報道もあり、今後は日本の台湾有事における立場が変わっていくことも考えられます。
台湾有事で危ない県・攻撃される場所はどこですか?
台湾有事が現実化した場合、日本本土が直接攻撃される可能性は低いとされています。
しかし、米軍が介入すればその拠点が狙われる可能性は否定できません。
中でもリスクが高いとされるのは沖縄県です。沖縄は台湾に近接しているうえ、嘉手納基地や普天間基地など米軍の主要拠点が存在します。そのため、有事の際には攻撃対象となる可能性があると指摘されているのです。
また、本州でも横須賀や三沢など米軍基地を抱える地域も、標的となるリスクはゼロではありません。
ただし、これはあくまでも「可能性」の話であり、必ず攻撃されるというわけではありません。
台湾有事で日本ではどれくらいの死者数が想定されていますか?
台湾有事における日本国内の死者数を想定したデータはありません。
台湾と中国の軍事衝突が日本本土に直接被害をもたらす可能性は限定的であり、日本政府や国際機関は「死者数」を具体的に試算してはいないのです。
まとめ|台湾有事による影響に備えるならHANAREにご相談を
本記事では、台湾有事における日本への影響について詳しく解説しました。
台湾有事は単なる国際問題ではなく、日本にとっても経済・安全保障の両面で大きな影響を及ぼす可能性があります。
海上輸送の混乱による物価上昇、半導体供給の停止による産業への打撃、そして沖縄など近隣地域の住民避難といった課題は、決して他人事ではありません。
もちろん「必ず起こる」と断定されているわけではなく、起こらないとの見解が多いのも事実です。
しかし、もし有事が現実化した場合、その被害は計り知れないものになります。だからこそ、日頃からの備えが重要です。
家庭でできる備えとしては、食料や水の備蓄、非常用持出袋の用意、避難計画の共有が挙げられます。そして最悪の事態に備える方法の一つとして注目されているのが、家庭用シェルターの導入です。
HANAREが取り扱うWNIシェルターは、日本での導入実績No.1を誇っており、核攻撃をはじめとするさまざまな有事に対応しています。
当社では、ご家庭やご予算に応じたシェルターを提案・設計・導入まで一貫してサポートしていますので、「台湾有事の影響が心配」「家族の安全を守りたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。




