台湾有事はいつ起こる?2025年・2027年説や個人ができる備えについて解説

近年、国際情勢の変化から注目を集める「台湾有事」。
もし中国と台湾の間で軍事的衝突が発生すれば、日本も経済面や安全保障の面で大きな影響を受ける可能性があります。
そのため、「台湾有事は本当に起こるのか?」「起こるとしたらいつなのか?」という不安を抱えている方も少なくないでしょう。
本記事では、台湾有事が「いつ起こるのか」という点について代表的な説を整理しつつ、起こる可能性や日本への影響、さらに個人としてできる備えについてわかりやすく解説していきます。
万が一の際に家族や自分を守るために、ぜひ参考にしてください。
■ 目次
台湾有事はいつ起こる?代表的な説2つ
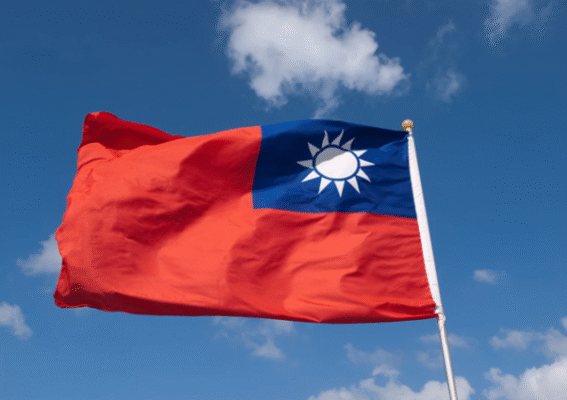
台湾有事については「すぐには起こらない」という見方もある一方で、専門家や海外メディアの間では特定の年を区切ってリスクを指摘する説が広まっています。
その中でも代表的なのが「2025年説」と「2027年説」です。
いずれも中国の軍事動向や国際情勢を背景に語られており、単なる憶測ではなく一定の根拠があります。ここでは、それぞれの説について、その背景や実際のリスクを見ていきましょう。
2027年に起こる説
2027年は、中国人民解放軍が創設100周年を迎える節目の年であり、習近平国家主席が掲げる「軍の近代化」の達成時期とも重なります。
そのため、中国はこの年までに台湾への軍事的圧力を強め、統一を実現しようとするのではないか、という見方が「2027年説」の背景です。
また、アメリカの軍事専門家の分析でも、中国が2027年までに台湾侵攻能力を完成させる可能性が指摘されています。
これは「必ず起こる」という意味ではありませんが、中国が軍事的な選択肢を手に入れる時期として注目されているのです。
ただし、中国自身も経済的リスクや国際的な孤立を避けたい思惑があり、必ずしも2027年に行動を起こすとは限りません。
むしろ、「2027年は一つの目安にすぎない」と理解しておくのが現実的でしょう。
2025年に起こる説
2025年説は、米軍内部から出た見解をきっかけに広まりました。注目されたのは、米空軍航空機動軍団のマイク・ミニハン司令官が同僚に宛てた内部メモです。
ミニハン氏はメモの中で「自分が間違っていてほしいが、2025年に中国と戦う予感がする」と述べ、米大統領選で米国が内政に気を取られる隙を中国が突く可能性を指摘しました。
この発言は個人の見解とされつつも、米軍内で台湾有事への警戒が強まっていることを浮き彫りにしています。
ただし、アメリカ国防総省は「個人のコメントは政府の公式見解ではない」と強調しており、2025年に必ず起こると断定できるものではありません。
むしろ、早期発生の可能性を念頭に抑止力を高める必要があるという危機意識が、こうした発言の背景にあると理解すべきでしょう。
台湾有事は起こらない?起こる可能性や確率は?

台湾有事については、専門家の間でも見解が分かれています。
近年、中国軍の動きや米中対立の激化から「近い将来に起こる」との見方が注目されていますが、一方で「実際には起こらない」とする意見も多く存在するのです。
「台湾有事は起こらない」と言われる理由のひとつは、軍事衝突が発生すれば中国自身も経済的に大きなダメージを受け、国際的に孤立するリスクが非常に高いためです。
輸出依存度の高い中国経済にとって、戦争は自国の利益を損なう「最悪の選択肢」と考えられています。
また、アメリカや日本をはじめとした同盟国の抑止力も、中国の軍事行動を思いとどまらせる要因となっています。そのため、現状では「すぐに台湾有事が起こる確率は低い」とされるのが一般的です。
ただし、可能性はゼロというわけではありません。中国は台湾統一を「核心的利益」と位置づけており、長期的に緊張が続くのは避けられない状況です。
台湾有事が起こる可能性は?起こらないと言われる理由や個人でできる備えを解説
いつ起こるかわからない台湾有事に備えて個人ができること
台湾有事は「起こらない」という見方も多い一方で、可能性がゼロではない以上、私たち個人は日ごろから有事に備えておくことが大切です。
ここからは、有事がいつ発生しても慌てずに対応できるよう、家庭でできる現実的な備えを整理していきます。
食料や飲料水、生活用品の備蓄

台湾有事が起これば、海上輸送ルートが混乱し、日本への輸入品が大きな影響を受ける可能性があります。
原油や穀物をはじめとした生活必需品の供給が滞れば、国内の物流にも連鎖的な混乱が広がり、スーパーやコンビニから商品が消える状況も想定されるでしょう。
そのため、家庭では最低3日、できれば1〜2週間分の飲料水や保存食を備蓄しておくことが推奨されます。
カップ麺やレトルト食品、缶詰、乾麺など、保存性が高い食品は災害時にも役立つので、日ごろから余裕をもって購入しておくとよいでしょう。
また、トイレットペーパーや電池、衛生用品といった生活必需品も確保しておくことも大切です。
これらの備えがあることで、物流が滞った際にも一定期間は安心して過ごせるでしょう。
避難先や避難行動、連絡手段の確認

台湾有事が発生した場合、日本国内で直接攻撃を受けるリスクは限定的とされています。
しかし、米軍基地が集中する沖縄など一部の地域では、攻撃に巻き込まれる可能性も否定できません。
そのため、万が一に備えるためには、自分や家族がどこに避難できるのかを事前に確認しておくことが大切です。
具体的には、自治体が指定する避難所や公共施設の場所を把握し、災害時と同じように避難経路を確認しておきましょう。
また、有事の混乱時には通信障害や回線の混雑が起こりやすいため、家族間で連絡手段を決めておくことも重要です。
例えば、「安否確認は災害用伝言ダイヤルを利用する」「連絡が取れないときは特定のSNSでメッセージを残す」といったルールを定めておくとよいでしょう。
避難先や連絡方法を家族で話し合って共有しておくことが、いざというときのスムーズな避難を可能にします。
家庭用シェルターの設置

台湾有事のように予測が難しいリスクに備えるうえで、最後の砦となるのが家庭用シェルターです。
家庭用シェルターとは、自宅の庭や地下、室内に設置できる避難設備のこと。ミサイル攻撃や放射性物質の拡散など、有事の影響が日本に及んだ場合でも、シェルターという安全空間を確保しておけば家族の安全を守ることができます。
また、小さなお子さまや高齢者がいる家庭では、避難所までの移動自体が困難なケースも少なくありません。その点、自宅内や敷地内に設置できるシェルターは「逃げ遅れ」を防ぐ現実的な選択肢といえるでしょう。
なお、近年では、従来の防空壕のような大規模な施設だけでなく、屋内に設置できる小型タイプや庭に置けるコンテナ型など、住宅事情に合わせた多様なシェルターが登場しています。
HANAREでは、住宅事情やご予算に合わせた最適なシェルターを提案させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
台湾有事に関するよくある質問
台湾有事という言葉を耳にする機会は増えましたが、「具体的に何を指すのか?」「日本にどんな影響があるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、台湾有事に関するよくある質問を取り上げ、それぞれについて詳しく回答します。似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで解消しておきましょう。
そもそも台湾有事とは何ですか?
台湾有事とは、中国と台湾の間で軍事的な衝突が発生する事態を指します。
中国が台湾の統一を目指して武力行使に踏み切った場合や、台湾海峡周辺で大規模な緊張が高まるケースを意味することが一般的です。
この問題が国際的に注目される理由は、単に台湾と中国の二国間の問題にとどまらないからです。
もし台湾有事が起これば、アメリカや日本を含む同盟国が関与する可能性が高く、アジア太平洋全体の安全保障や世界経済に重大な影響を及ぼすと考えられています。
詳しくは、以下の記事でも解説していますので、あわせて参考にしてください。
台湾有事とは?日本への影響や起こる可能性、個人でできる備えをわかりやすく解説
台湾有事による日本への影響は?
台湾有事が発生した場合、日本は地理的にも経済的にも無関係ではいられません。
まず大きな影響が出ると考えられるのが 貿易や物流の混乱です。
台湾海峡は日本のエネルギー資源や食料を運ぶ重要な海上輸送ルートであり、ここが封鎖されれば原油や小麦などの輸入に支障が出て、燃料費や食料品の価格高騰につながる可能性があります。
また、台湾は世界的な半導体生産拠点であり、日本企業も多くの部品を輸入しています。有事で供給が止まれば、自動車や家電、スマートフォンなど幅広い産業が打撃を受けるでしょう。
さらに、台湾や中国に滞在する日本人の安全確保や避難支援も大きな課題となります。
なお、台湾有事による日本への影響については、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
台湾有事で攻撃される場所はどこですか?特に危ない県は?
台湾有事が現実化したとしても、日本が直接攻撃を受ける可能性は高くはないとされています。
しかし、アメリカが介入した際には、その拠点となる在日米軍基地が標的となるリスクはゼロではありません。特に、沖縄には嘉手納基地や普天間基地などの重要な施設が集中しており、最前線に近いことから攻撃を受ける可能性は否定できないでしょう。
実際、沖縄県内では有事に備えた住民避難計画が策定されており、12万人規模の島民が一時的に退避するシナリオも検討されています。
| いわゆる「台湾有事」などを念頭に、政府は、沖縄の離島からの避難計画を初めてまとめ公表しました。住民らおよそ12万人を6日程度で避難させ、九州や山口県の合わせて32の市や町で受け入れるなどとしています。 |
ただし、こうした議論はあくまでも「可能性の一つ」であり、現時点で日本が直接攻撃されると断定できるものではありません。
重要なのは、リスクを理解したうえで冷静に備えることです。沖縄や西日本に住む方は、自治体の避難計画や安全情報を常に確認しておくと安心でしょう。
台湾有事での日本の死者数はどれくらいと想定されますか?
台湾有事に関連して「日本での死者数」が公式に想定されているわけではありません。
これは、日本が直接戦闘の舞台になる可能性は低く、あくまでも台湾海峡やその周辺が主な衝突の場と考えられているためです。
ただし、在日米軍基地を抱える沖縄など一部地域が攻撃対象となるシナリオは否定できません。その場合、地域住民の被害が発生するリスクは存在しますが、具体的に想定される死者数のデータなどは公表されていないのが現状です。
まとめ|いつ起こるか台湾有事に備えるならHANAREにご相談を
台湾有事は「2025年説」「2027年説」といった具体的な年が取り上げられる一方で、実際に起こるかどうか、そして起きるとしたらいつなのかは誰にも断定できません。
多くの専門家は「当面は起きにくい」との見方を示していますが、米中対立の激化や地域情勢の変化によって、リスクが高まる可能性は常に存在しています。
そのため、私たちにできる最善の対応は「いつ起きても慌てないように備えておくこと」です。
食料や飲料水の備蓄、避難計画や連絡手段の確認、非常用持出袋の準備など、できることから始めておくことで安心につながります。
さらに、最悪の事態に備えるなら家庭用シェルターの設置も現実的な選択肢となるでしょう。
なお、HANARE ではご家庭の状況に合わせたシェルターの導入を提案しています。「台湾有事のリスクに備えたい」「具体的にどんな準備をすべきか相談したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。




